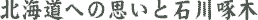
東京も寒さの季節です。でも、寒いのもいいもの。きりっと緊張感がありますし、家に帰り、温かい空気に触れるとほっとしたりもします。
初めて北海道に行った時、千歳空港から札幌に向かうと、100年以上も前に、こんな極寒の地に道を通し、家を建て、街を創った人たちがいたのだとの感慨深かったものです。この地は明治維新の直後、独善的な傾向を強める薩長中心の政府に異議申し立てをした榎本武揚らが独立を夢見たところでもあります。
その後も、何度か小樽も訪ねたことがあります。小樽は坂のある街で、駅前の坂を下っていくと、あっという間に港に行き着きます。
小樽というと、石川啄木を思い出します。彼は、この街で、小樽日報社に職を得て、沢山の歌を残しています。2006年には生誕120年を迎えました。
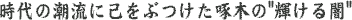
ある企業の広報誌編集のため、北海道開拓の歴史を調べたことがありました。その際に知ったのですが、主に北海道の開拓を担ったのは幕末の戊辰戦争などで領地を失った旧幕府側の人たちでした。負けた側の人たちが、新しい夢を北の大地に託したのです。
そんなこともあるのか、石川啄木が暮らした頃の小樽には進取の気風も強くあり、啄木は、日記に「小樽に来て初めて真に新開地的な、真に植民地精神の溢るゝ男らしい活動を見た。男らしい活動が風を起す。その風が即ち自由の空気である。」と書いています。
 そして、「一握の砂」の中で詠ったのが、 そして、「一握の砂」の中で詠ったのが、
こころよく我にはたらく仕事あれ
それを仕遂げて死なむと思ふ
です。
彼の文学的な才能を疑う人はいないでしょう。ただ、好き嫌いはあるようです。何故かと考えると、素直でなく、ひねくれているからでしょう。
この歌にしても、せっかく小樽の地で仕事を得たのに、後段で、大げさにも「それを仕遂げて死なむと思ふ」といっています。でも、この一見すると、アンバランスな感覚が魅力だともいえます。言葉をかえると、後段で内省しているともいえるからです。
彼の歌は抒情的過ぎて嫌いだという人もいるでしょう。抒情とは、何かの過剰か、欠乏によって強まります。表面的にはただ甘ったるいだけです。彼の歌が、何故、後生まで残ったのかといえば、この過剰と切望への内省にあるといえます。そして、小樽を歌った歌には、
かなしきは小樽の町よ
歌ふことなき人々の声の荒さよ
の代表作もあります。結局、彼は「自由の空気」には触れたけれど、港町の小樽の「男らしさ」には違和を覚えたのか、短期間、滞在し、家族も残したまま、釧路に旅立ちます。
「一握の砂」の題にもなったのが、あまりにも有名な
いのちなき砂のかなしさよ
さらさらと
握れば指のあひだより落つ
です。
これは恐ろしい歌です。どうしようもない程の喪失感はとてもよくわかります。きっと誰にも共通する感覚でもあるでしょう。それでも、ただの喪失感だけではありません。彼の歌のもう一つの特徴でもある自己慰安があります。自己で慰安しなければならないほど、生前は報われることもなく、極貧の生活でした.。
一方で、彼は「大逆事件」が起こるなど政治的な時代にも生きていました。彼の内省はやがて社会的な関心に移っていきます。そして、書き下ろしたのが「時代閉塞の現状」です。当時の社会のあり方を、文学の一潮流であった「自然主義」との関連で評論しています。彼の抒情の背景には、厳しい内省があり、そして、ただの自己慰安だけの歌人でなかったことは、知っておきたいものです。
彼は夭折しています。あのまま生きていたとしても、社会的な関心を延長し、政治的な活動をしたかというと、そうではなかったはずです。彼は政治的な、そしてその中で生まれる人間関係の葛藤には耐えられなかったはずだからです。その意味では夭折してしまったのは彼にとっては幸福であったのかもしれません。
そんなに甘っちろいもんじゃないよ。優しさなんて何の有効性もないよ。日々の生活はそんなもんじゃないよ、との声も聞こえてきます。それでも、誰もが、ある時は、自己慰安を必要としていますし、弱いものに対してはっとシンパシーをもったりします。
しかし、それはすぐに消えてしまい、少しばかりの後ろめたさをもったりするものです。石川啄木の歌は、そんなことを考えさせます。
|

