|
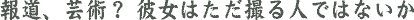
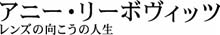 アニー・リーボヴィッツ
レンズの向こうの人生(原題:ANNIE LEIBOVITZ: LIFE THROUGH A LENS)。 アニー・リーボヴィッツ
レンズの向こうの人生(原題:ANNIE LEIBOVITZ: LIFE THROUGH A LENS)。
 今、世界で一番有名な女流写真家アニー・リーボヴィッツの半生を描いたドキュメンタリー。彼女を一躍、有名にした二枚の写真がある。 今、世界で一番有名な女流写真家アニー・リーボヴィッツの半生を描いたドキュメンタリー。彼女を一躍、有名にした二枚の写真がある。
全裸のジョン・レノンが黒いセーターとジーンズのオノ・ヨーコに、しがみつくように寄り添う写真。1980年12月8日、撮影の数時間後にジョンは暗殺された。彼の最後の一日を留めた写真は、1981年1月に特別追悼号として刊行されたローリングストーン誌の表紙を飾った。
妊娠中の大きなお腹を抱えたデミ・ムーアのヌード写真。ファッション誌ヴァニティ・フェアの表紙に選ばれ、ワイセツか母性への賛美かと世界中に大論争を巻き起こした。米国では掲載誌が発売禁止処分になった州もあった。
2月16日(土)よりシネマGAGA、シネカノン有楽町2丁目ほか全国順次ロードショー。

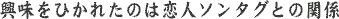
『報道と芸術、その両キャリアにおいて天才だったアニー・リーボヴィッツの驚きの旅路が描かれる』ハリウッド・リポーター誌。
 彼女は、ミュージシャン、映画スター、政治家、実業家、ダンサー、スポーツ選手など、セレブリティたちの写真を数多く、撮影している。 彼女は、ミュージシャン、映画スター、政治家、実業家、ダンサー、スポーツ選手など、セレブリティたちの写真を数多く、撮影している。
彼らは、「アニーは特別だ」と語り、セレブリティたちの思いがけない表情と裸になった心が写っていると評されている。
巨額な資金が消費される生き馬の目を抜くような虚飾の世界。彼女に撮してもらえれば、話題性も高まり、効果的なプロモーションにもなる。持ちつ持たれつの関係、双方了解済みの公認パパラッチのようなもの。心地よいものではなかった。
興味をひかれたのは別の側面だ。1993年、彼女は恋人のスーザン・ソンタグに誘われセルビア軍に包囲されたサラエボに同行する。
最初に訪れたのは死体置き場だった。死体袋からはみ出した若い男の顔は、血にまみれ、恨めしそうに目を開いている。白い布にくるまれた小さな遺体もある。多くの子供たちが命を失っていた。彼女は、自分に何が撮れるか怖かった、サラエボから帰った直後は、セレブリティたちの撮影など、何の意味もないと思ったと語っている。
彼女の仕事場の壁には、写真が所狭しと貼られていた。写真集出版のために写真選びをしていたのだ。家族、スーザン・ソンタグ、セレブリティたち、そしてサラエボの写真。編集のために分類されたさまざまな写真があった。写真家とはどのような存在なのか。そして、彼女は何者なのか。写真とは何かというテーマを否応なしに考えさせる。
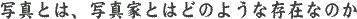
2001年、ソンタグがオックスフォード大学で講演「戦争と写真」を行った。ソンタグは、写真にできること、できないことを冷静にかつ明確に語った。
アニーとの出合いは、1989年頃といわれている。その前にソンタグは「写真論」を発表している。写真とは何か、それを追求する中で、二人の関係は深まっていったのだろうか。
写真とは何か。何を撮るのか、人物にしろ、風景にしろ、世界の一部を撮影者の意図で切り取る。逆説的にいえば、全ては映らないし、その写真から何がはみ出しているのか、何を映していないのかも重要だ。
更に写真とは何かを複雑にしているのが、特に商業写真の場合、最近では、デジタル技術を用いた編集が伴うことだ。かつては著名な写真家には、専属の現像技師がいた。現像段階でも、写真は対象を変容させることもできた。
どのメディアに掲載されるのかも大切なポイントだ。有名メディアであれば、大量に複製が消費され、強い影響力を発揮するという面もある。
初めてニコンの一眼レフを手に入れた時、リバーサルフィルムで花を撮影した。現像所から戻ってきたリバーサルフィルムを光にかざして見ると、とても綺麗だった。その瞬間、写真は現実をそのまま写し取るのではなく、現実を修飾することもあると思った。
 セレブの撮影シーンでは、スパイダーマンのヒロイン役のキルスティン・ダンストが繰り返し、登場する。キルスティン・ダンスト出演の映画「マリー・アントワネット」を題材としたヴォーグ誌に向けた撮影シーンだ。編集者が語っている。「彼女の撮影は予算は度外視している」と。 セレブの撮影シーンでは、スパイダーマンのヒロイン役のキルスティン・ダンストが繰り返し、登場する。キルスティン・ダンスト出演の映画「マリー・アントワネット」を題材としたヴォーグ誌に向けた撮影シーンだ。編集者が語っている。「彼女の撮影は予算は度外視している」と。
ここでまた写真とは何かを考えさせられる。そこにある世界の一部をありのままに切り取るのではなく、撮影対象にあらかじめ演出を加え、再構築してしまう。そこに彼女の独自性、企画性があるとしても、写っているのは、現実では考えられない、夢のような光景。すでに写真の領域を越え、絵画を描くかのような行為ともいえる。彼女の写真は、そんなさまざまな要素を内包している。
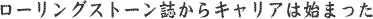
彼女の写真家デビューのきっかけは、1970年、ローリングストーン誌の編集部訪問に始まる。60年代のサンフランシスコ。彼女は当時の風俗を捉えた大量の写真を編集部に持ち込み、必死でジョン・レノンへのインタビュー撮影の仕事を獲得した。無名のアニーに優しく心を開くジョンとの出逢いが、彼女のその後を決定づけた。
1975年には、ローリングストーンズのツアーに密着し、それまで誰も見せたことのない彼らのバックステージをとらえた。1977年、メジャーな雑誌へ成長したローリングストーン誌はニューヨークへ移る。
彼女が出会ったのは、出版デザインの分野でカリスマ的存在のビア・フェイトラー。それまでローリングストーン誌の表紙は、ミュージシャンを並べて撮っただけの写真だった。ビア・フェイトラーは、それを「とんだ大失態」と叱責する。
ここから彼女は、写真ごとにある種のコンセプトを加える手法を考え始める。何千本ものバラの上に寝そべるベット・ミドラー、顔を青くペイントしたブルース・ブラザース、燃え盛る炎の前に立つパティ・スミス。彼女は、写真の中にストーリーやメッセージを加え始めた。
何を切り取るのではなく、撮るべき対象に演出を加え、一瞬だけ、独特な世界を構成する。そこに映るのは、ありのままの世界ではなく、虚構の世界だ。一方で、その虚構の方がリアルに感じる。それはセレブと賞される人たちの存在感に依存している。
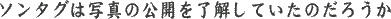
最も印象的だったのは、死の床に横たわるスーザン・ソンタグの姿だった。アメリカを代表する知識人の一人、批評家、小説家、映画監督として活躍した彼女。優れた知性にも終焉が訪れる。ソンタグは、この写真の公開を了解していたのかとの疑問をもった。
2004年12月28日、享年71歳。訃報は世界各国に流れた。米国の現状もあり、ソンタグへの評価はまだ定まっていない。
1966年に出版の最初の評論集「反解釈」で既存の批評の立ち位置を批判するという攻撃性でセンセーションを巻き起こす。1968年、ハノイに渡り、「ハノイで考えたこと」を出版、ベトナム戦争反対の活動でも知られた。その後、40年もの間、彼女が何を書くか、どう語るかが注目された。
1999年、「すべての戦争が等しく不正なものなのでもない」とNATOによるセルビア爆撃を支持、この論説を巡り、大江健三郎との往復書簡が朝日新聞に掲載され、日本でも話題を呼んだ。9.11では、ニューヨーカー誌に「これは文明や自由や人間性に対する攻撃ではない。自称"超大国"への攻撃だ」と書き、彼女は変身したのかとアメリカで物議を醸した。
アニーがソンタグのどこに惹かれたのかはわからない。それは個人に属するからだ。彼女はソンタグの死の喪失を埋めるかのように、50歳代になり、妊娠、出産を経験している。そして、デミ・ムーアのような写真も撮影している。
ソンタグの影響を受け、彼女は社会性に目覚めたとの論もあるが、違うと思う。2007年、ルイ・ヴィトンの秋の広告。元ソビエト連邦大統領ゴルバチョフを起用し、話題を呼んだ。
その写真をを見るものは、年老いたゴルバチョフの姿に一種の社会性を感じさせれらる。これもうがった見方だ。そのままではルイ・ヴィトンの思惑に乗せられてしまう。彼女の写真そのものに社会性があるのではなく、それは撮られる側に依存している。彼女は、ただ撮す人なのだ。
◆監督・製作:ーバラ・リーボヴィッツ
◆製作総指揮:ポール・ハーダート、トム・ハーダート、スーザン・レイシー
◆音楽:ゲイリ・ショーン
◆写真監督:ディ・マリッツ、ジェイミー・ヘルマン、バーバラ・リーボヴィッツ
◆キャスト:オノ・ヨーコ、キルスティン・ダンスト、デミ・ムーア、キース・リチャーズ、アナ・ウィンター、ヒラリー・クリントン、ミック・ジャガー、アーノルド・シュワルツェネッガーウーピー・ゴールドバーグ、パティ・スミス、ミハイル・バリシニコフ、ベット・ミドラー、ロザンヌ・キャッシュ、マーク・モリスほか
◆2007年アメリカ/83分
◆配給:ギャガ・コミュニケーションズ powered
by ヒューマックスシネマ
◆公式ホームページ
Photographs (C) 2007 by Annie Leibovitz.
|

